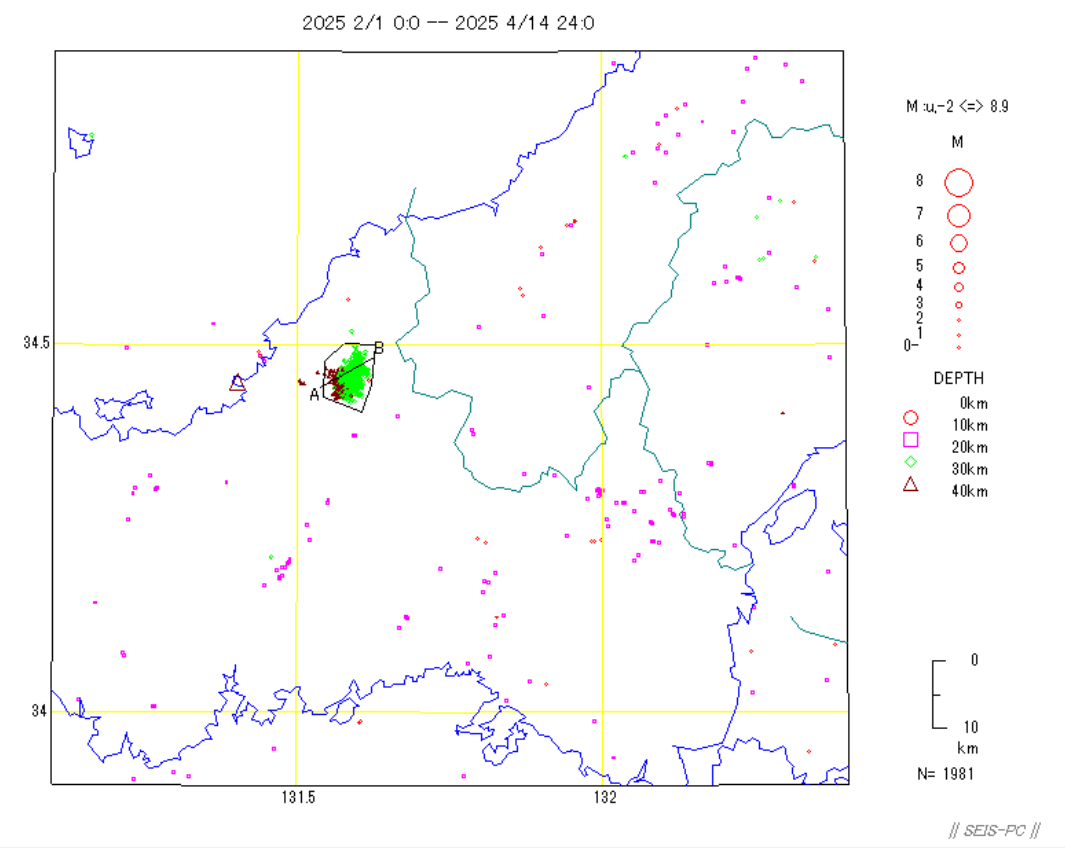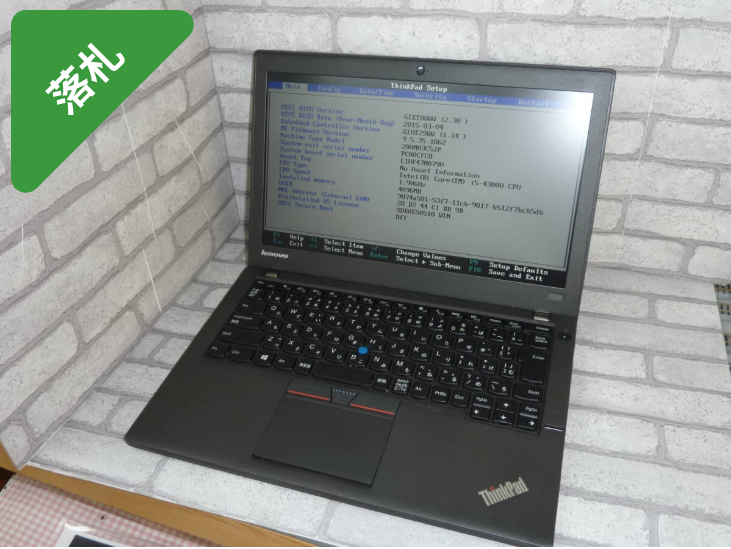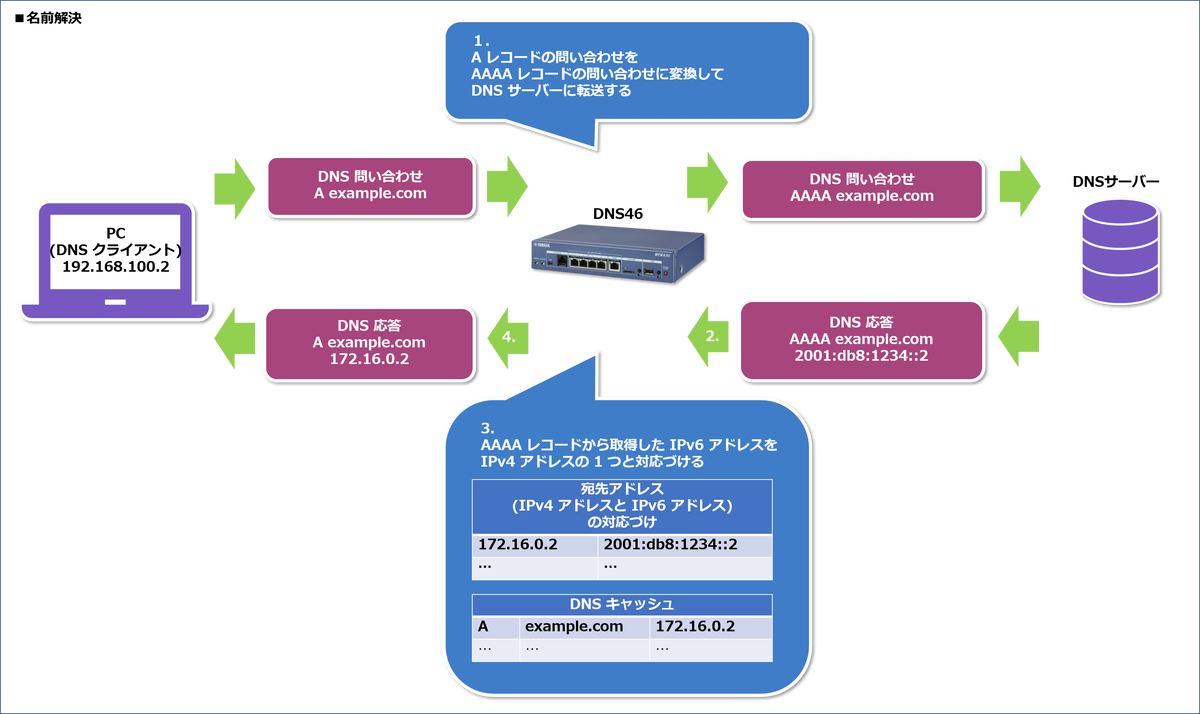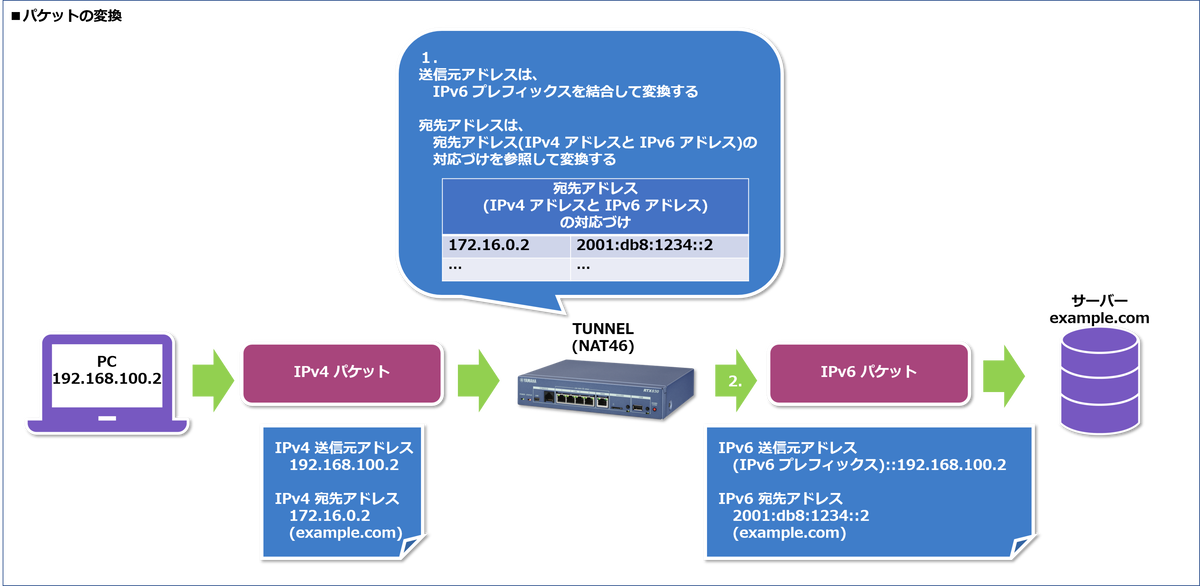- (3)4月30日東海道新幹線で停電
岐阜羽島と米原間で停電が発生.
原因は「蛇」が高圧線に触れて遮断機が動作したらしい。
通常架線を支える電柱には蛇除け装置が設置してあります。

図 蛇返し
新幹線の場合おそらく電柱から上ったであろうとおもわれます。
電柱にアース線のような配線があったのではないでしょうか。
新幹線の蛇対策を徹底していただきたい。
私が勤めていたころ会社に給電している高圧線に蛇が昇り送電線がシャットダウンしました。
このため操業は止まり材料工程の仕掛品はすべて廃棄処分となりました。
電力会社の補償はありませんでした。